相続税の配偶者の税率って何%?税金を減らすための方法とは?
相続税。
このように聞いた場合に、
どのようなイメージを持ちますか?
「自分はそんな財産持っていないから大丈夫。」
そんなふうに思う人も多いのではないでしょうか。
あまり考えたくはない話ではありますが・・・
でも、万が一、夫婦でどちらかが無くなってしまった場合に、
家を持っていたり、証券を持っていて資産がそれなりになった場合。
いったい、配偶者の相手(もしくは自分)には、
どれくらいの相続税の支払いが必要になるのでしょうか。
もし自分が亡くなってしまった場合に、
残された家族が払わないといけなくなる税金はどれくらい?
はたまた、自分の配偶者が亡くなってしまった場合に、
いったいいくらのお金が税金としてかかるのか。
しかも、平成27年より相続税法が改正になり、それまで相続税を
払わなくてよかった人も相続税の対象になる可能性がでてきたのです!
あまり考えたくはない、死後のお金の話。
でも、知識として知っておくことで、
避けられる不幸もあります。
と、いうことで!
今回は相続税の仕組みや、
相続税を節税する方法をご紹介いたします。
それではさっそくみていきましょう!
相続税と贈与税
相続税の話の前に、一つ覚えておきたい税金があります。
それは、贈与税。
相続税と贈与税はどう違うのでしょうか?
これは簡単です。
- 贈与税
財産を保有する人が生きているうちにお金や物等の財産価値があるものを無償で譲渡する場合にかかる税金。
- 相続税
亡くなってから無償で譲渡が行われる例にかかる税金。
どちらも無償で譲渡することに係る税金であることに違いはありません。
しかし、相続税を基本として法整備がなされているため、
贈与税は相続税の補完税という関係性になっています。
では税率はどのようになっているのでしょうか?
次に相続税と贈与税の税率を見ていきたいと思います。
相続税の早見表と基礎控除額
相続の計算は独特です。
早見表がありますが、亡くなった方の家族構成により、
初めに課税される財産より差し引かれる基礎控除が変わってきます。
簡単に言えば、財産が基礎控除より少なければ、
相続税を払わなくてもよいし、申告の必要もありません!
基礎控除の計算式は3,000万円+(法定相続人×600万円)で計算されます。
法定相続人とは基本的には配偶者と子供と思っていただければOKです。
(子供がいない場合は父母などになります。)
平成27年以前は5,000万円+(法定相続人×1,000万円)でしたので、
相続税を支払う世帯は全体の4.4%でした。
それに対して、平成27年に相続税が課税になった世帯は
全体の8%におよび、課税を受ける世帯が約2倍に膨らんでいます。
では基礎控除を差し引いたあとの税率はどうなっているのでしょう。
以下の表が相続税の早見表です。
| 法廷相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 20万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超え | 55% | 7,200万円 |
例をあげてみましょう。
被相続人(亡くなった方)の家族構成が、
相続税はどうなるでしょう?
まずは基礎控除の計算をします。
3,000万円+(600万円×3人(妻、子供2人))=4,800万円
1億円から4,800万円の基礎控除を差し引いて、
5,200万円について相続税がかかる財産になります。
次に5,200万円についての相続税の総額を仮に計算していきます。
法定相続持分により妻は1/2、子供は1/4の持分となります。
(仮)
妻分 5,200万円 × 持分1/2 = 2,600万円
早見表より(2,600万円 × 税率15%)- 50万円 = 340万円
(仮)
子供1分 5,200万円 × 持分1/4 = 1,300万円
早見表より(1,300万円 × 税率15%)- 50万円 = 145万円
子供2分も同様に145万円となります。
合計額340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円
この家族構成で1億円の相続資産に係る相続税は630万円ということになります。
しかし!
相続税には配偶者控除という制度があります。
配偶者控除はなんと1億6000万円、
または配偶者の法定相続分相当額のどちらが高い方が控除できる制度です。
この場合、妻が全ての財産を相続してしまえば課税財産は5,200万円で、
1億6,000万円より低いため、相続税額は0円になります。
全ての財産でなくとも妻が相続した額が多いほど世帯の総納付税額は低くなります。
例えば妻が8,000万円相続し、子供2人が1,000万円ずつ相続した場合は、
- 妻の相続財産が1億6,000万円以下のため税額は0円。
各子供は、
相続税の総額630万円 × 1,000万円/1億円 = 63万円の相続税の納付
となり、
2人で合計126万円の相続税になります。
このように、配偶者控除をうまく使うことで相続税の納付額を下げる、
または税額を0円にすることが出来ます!
Sponsored Link
相続税を減らすためには
相続税を減らすには配偶者控除をうまく使うことも有効です。
しかし、二次相続(次に妻がなくなった場合は、配偶者がいないため配偶者控除が使えない。)
を考えて早めに相続税の対策をする必要があります。
相続税を軽減するのによく使われる方法が贈与税の基礎控除を利用する方法です。
贈与税は相続税に補完税と説明した通り、贈与税は相続税に影響を与えます。
贈与税の申告は、無償で譲渡を受けた人がその年に申告する税金なのですが、
贈与税においても基礎控除が存在します。
贈与税の基礎控除は1人年額110万円です!
1年間で110万円の贈与を受けても申告する必要も、
贈与税を納める必要もありません。
「なんだ110万円じゃ全然足りないじゃん。」
と思った人もいるのではないでしょうか。
ですが贈与を10年間していったらどれぐらいの額になるか計算してみましょう。
さっきの例でいうと、
被相続人(亡くなった方)が10年前より家族3人(妻、子供2人)に年額110万円贈与したとします。
(生前贈与3年以内加算は考慮していません。)
10年 × 3人 × 110万円 = 3,300万円
つまり、3,300万円分の相続財産が減らすことが出来るのです。
合計税額を比較してみると以下の通りです。
- 妻分:1900万円 × 持分1/2 = 950万円
早見表より950万円 × 税率10% = 95万円
子供1人分:1900万円 × 持分1/4 = 475万円
早見表より(475万円 × 税率10%) = 47.5万円
子供2分も同様に95万円となります。
合計額95万円 + 47.5万円 + 47.5万円 = 190万円
以前の合計税額は630万円でしたので440万円も税額が違うことになります。
このように、所持しているお金の総額は同じでも、
生前にどのように管理するかによって、将来引かれる税額も変わってくるのです。
Sponsored Link
まとめ
今回は、夫婦間で将来どちらかが亡くなった場合にかかる
相続税の配偶者の税率が何%なのか。
また、将来かかる税金を減らすための方法について紹介しました。
相続税と聞いて頭が痛くなる人もいるかもしれません。
ですが、事前に長いスパンで子供や孫に対する贈与をすることにより、
贈与税の基礎控除を利用した相続税額の節税が可能なのです。
早く対策をすればするほど相続税を減らすことが出来るので、
悩んでいる方は一度税理士にご相談されることをおすすめします。
今回は以上です。
ご参考になりましたら幸いです。
(*゚ー゚*)ノ
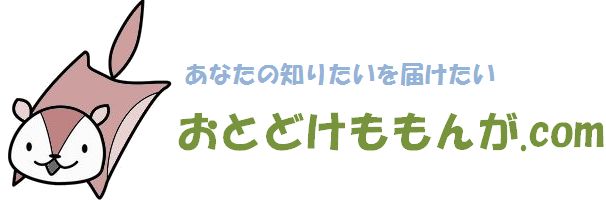




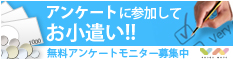
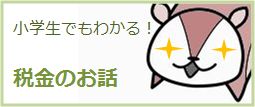
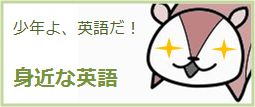
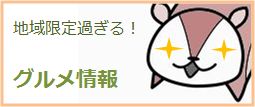
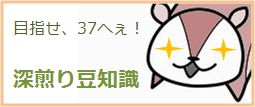
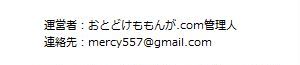
最近のコメント